生体膜物質輸送は、細胞そして生体の恒常性維持の基本である。それを担う輸送分子(イオンチャネル、トランスポーター、ポンプ)の研究は、個々の輸送現象の計測から始まり、分子実体の解明に到達したものの、近年では予想を超えた多くの難問に遭遇している。例えば、輸送分子のノックアウトマウスの表現型において、輸送分子の単純な欠損では解釈が成立しないシグナル系への機能異常の波及などが観察され、単なる他サブタイプ輸送分子による補完作用のみでは説明不可能な多面的影響が多く報告されている。これらの最近の断片的データを総合的に理解するためには、『生体膜物質輸送の機能単位は、個々の「単一輸送分子」ではなく、様々な相互作用によって関係しあった輸送分子群、機能制御分子群、それを束ねるscaffold(「足場」)タンパク質群からなる生体膜物質輸送複合体(「トランスポートソーム」)である』という基本概念を導入する必要がある。
また、生体膜上のトランスポートソームの分子集積を解明するためには、それを支える膜脂質、細胞骨格を含めた作動環境にどのように依存するか、トランスポートソームが細胞内において情報伝達系とどのようにクロストークし、ホルモンや神経伝達物質などにより調節され、生体の恒常性維持に寄与しているか、を知る必要がある。従って、生体膜物質輸送を包括的に理解するためには、「単一輸送分子」から「分子複合体」という新たな観点へと研究を発展、深化させ、その分子構築、作動環境との相互作用、調節とシグナル系とのクロストーク、組織や個体レベルでの生理機能及び病態との関連を統合的に明らかにすることが不可欠である。
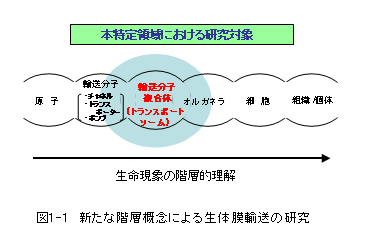 細胞膜は、細胞の内外を隔てる物理的隔壁であると同時に、内外の物質環境の橋渡しをする重要な役割を持つ。すなわち細胞膜は、内外の物質の直接のやり取りを媒介するとともに、外部環境の変動を察知し、その情報を内部へと伝える。従って、細胞膜の主な能動的機能は、「物質輸送」と「情報伝達」に集約できる。情報伝達については、受容体研究の延長上に、受容体とシグナル分子が集積する情報変換装置「シグナロソーム(signalosome)」の概念が確立され、情報伝達の機能ユニットとして認知されている。膜の能動機能のもうひとつの柱である「物質輸送」においても、単一輸送分子の研究から次の段階へのブレークスルーを模索する過程で、分子複合体の概念の必要性が出てきている。すなわち、輸送分子群、輸送機能制御分子群、それを束ねるscaffoldタンパク質群が集積する、物質輸送の機能ユニットとしての分子複合体である。これを「トランスポートソーム(transportsome)」と呼ぶ。トランスポートソームは、「ナノマシーン」としての輸送分子とオルガネラの中間に新たに設けられた「分子と生体を結ぶ階層」であり、生理機能、病態を分子の言葉で理解する上で、必須の実体である(図1-1)。「単一分子」のアプローチで現在現れてきている矛盾点や未解決の問題は、分子複合体のレベルの現象が露わになってきたものと考えられ、これらの解決は、複合体を単なる分子の加算としてではなく、集合体となって始めて顕れる固有機能を持つ階層として捉え、その挙動を支配する法則を見出すことによってしか達成されない。「トランスポートソーム」研究は、以上の考えに立脚する。
細胞膜は、細胞の内外を隔てる物理的隔壁であると同時に、内外の物質環境の橋渡しをする重要な役割を持つ。すなわち細胞膜は、内外の物質の直接のやり取りを媒介するとともに、外部環境の変動を察知し、その情報を内部へと伝える。従って、細胞膜の主な能動的機能は、「物質輸送」と「情報伝達」に集約できる。情報伝達については、受容体研究の延長上に、受容体とシグナル分子が集積する情報変換装置「シグナロソーム(signalosome)」の概念が確立され、情報伝達の機能ユニットとして認知されている。膜の能動機能のもうひとつの柱である「物質輸送」においても、単一輸送分子の研究から次の段階へのブレークスルーを模索する過程で、分子複合体の概念の必要性が出てきている。すなわち、輸送分子群、輸送機能制御分子群、それを束ねるscaffoldタンパク質群が集積する、物質輸送の機能ユニットとしての分子複合体である。これを「トランスポートソーム(transportsome)」と呼ぶ。トランスポートソームは、「ナノマシーン」としての輸送分子とオルガネラの中間に新たに設けられた「分子と生体を結ぶ階層」であり、生理機能、病態を分子の言葉で理解する上で、必須の実体である(図1-1)。「単一分子」のアプローチで現在現れてきている矛盾点や未解決の問題は、分子複合体のレベルの現象が露わになってきたものと考えられ、これらの解決は、複合体を単なる分子の加算としてではなく、集合体となって始めて顕れる固有機能を持つ階層として捉え、その挙動を支配する法則を見出すことによってしか達成されない。「トランスポートソーム」研究は、以上の考えに立脚する。
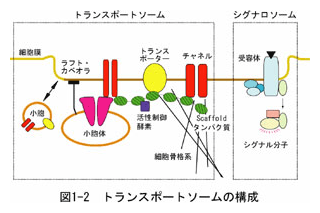 トランスポートソームは、単なる操作上の概念ではなく、実体を伴うものと推定される。最近の幾つかの先導的な研究が輸送分子を巡るタンパク質間作用の解析に乗り出し、異なる多くの輸送分子が共通のscaffoldタンパク質に結合することを見い出した。例えば、哺乳類の腎臟尿細管においては、 scaffoldタンパク質に、異なる機能と異なる構造を持つ複数種の輸送分子が結合しうることが示された。これらのscaffoldタンパク質は、さらにアダプター分子を介し細胞骨格にアンカーする。一方、輸送分子の幾つかは細胞膜ラフト画分に存在するという別の報告も存在する。以上の知見を総合すると、ラフト、カベオラ等の細胞膜ミクロドメインや細胞骨格をプラットホームとして、輸送分子とその制御分子のセットが、scaffoldタンパク質に束ねられて集積し、「トランスポートソーム」を形成するという考えに行き着く(図1-2)。他の組織においても「トランスポートソーム」を想定することにより、従来の生理学研究で明らかにされた多くの輸送分子間の機能的協関に明確な説明を与えることが可能であり、本申請領域の「トランスポートソーム」が実体を持っているという考えが支持される。
トランスポートソームは、単なる操作上の概念ではなく、実体を伴うものと推定される。最近の幾つかの先導的な研究が輸送分子を巡るタンパク質間作用の解析に乗り出し、異なる多くの輸送分子が共通のscaffoldタンパク質に結合することを見い出した。例えば、哺乳類の腎臟尿細管においては、 scaffoldタンパク質に、異なる機能と異なる構造を持つ複数種の輸送分子が結合しうることが示された。これらのscaffoldタンパク質は、さらにアダプター分子を介し細胞骨格にアンカーする。一方、輸送分子の幾つかは細胞膜ラフト画分に存在するという別の報告も存在する。以上の知見を総合すると、ラフト、カベオラ等の細胞膜ミクロドメインや細胞骨格をプラットホームとして、輸送分子とその制御分子のセットが、scaffoldタンパク質に束ねられて集積し、「トランスポートソーム」を形成するという考えに行き着く(図1-2)。他の組織においても「トランスポートソーム」を想定することにより、従来の生理学研究で明らかにされた多くの輸送分子間の機能的協関に明確な説明を与えることが可能であり、本申請領域の「トランスポートソーム」が実体を持っているという考えが支持される。
以上のような状況を鑑み、「トランスポートソーム」の概念のもとに「次世代の膜輸送研究」を推進し、大きなブレークスルーを期待するには、単なる散発的な研究の累積では限界がある。生体膜輸送複合体の解明を目指した共通の問題意識を持ち、異なった研究基盤と解析技術を持つ研究者からなる学際的研究を組織、推進することが必須である。また、近年のプロテオミクス技術、分子可視化技術の革命的な進歩により、分子複合体の解析的研究が可能となり、「トランスポートソーム」研究の実現性が保証されたことも、本特定領域研究の重要な背景となっている。本特定領域研究は、5年間の研究期間において、個々のトランスポートソームの分子構築と機能を解析することにより、構成分子、空間的広がり、動態、及びその形成に関わる分子間相互作用ネットワークを明らかにし、トランスポートソームの実体を解明すること第一の目標とする(A01)。トランスポートソームは、生体膜上の適切な位置に配置されることが必要であり、またその機能はその作動環境に大きく影響されるため、トランスポートソームとそれが形成されるプラットホームである細胞膜ミクロドメインや細胞骨格との相互作用を明らかにし、トランスポートソームの生体膜上での存在の様式と機能発現における作動環境の役割を解明することを第二の目標とする(A02)。さらに、トランスポートソームの調節とシグナル系とのクロストーク、及び細胞、組織、個体における生理機能とその破綻により生じる病態との関わりを解明し、輸送分子が単独で存在するのでなく、トランスポートソームの中に分子複合体の一員として組み込まれて存在することの意義を明らかにすることを第三の目標とする(A03)。 トランスポートソーム研究は、細胞から個体レベルの恒常性の理解に不可欠な知見を提供することにより、基礎生物学、生理学の発展へ多大な寄与をすることができる。また、シグナル伝達系とのクロストークの解明により、細胞生物学領域での重要度はますます高まると考えられる。さらに、トランスポートソーム研究は、分子と生体を結ぶ必須の情報を提供するため、極めて大きな臨床医学への貢献が可能であり、研究成果が現在明確な理解が得られていないヒトcommon diseases等の多因子疾患の理解に新たな視点を導入するものと期待される。
生体膜輸送の研究は、生命現象と分子の対応付けを目指す分子生物学的手法の導入により、大きくブレークスルーし、輸送分子の実体解明、遺伝性疾患との関連付けが急速に進展した。この方向性は、輸送分子の三次元構造の解明を目指す研究によってさらに受け継がれ、発展が継続している。しかし、研究の出発点であった『膜輸送の生理的な機能は何か』という最重要課題に対しては、すでに述べたように「単一分子」の研究は多くの問題を積み残す結果となった。「トランスポートソーム研究」は、「生命現象と分子複合体の対応付け」を主導原理として、生体膜輸送研究を牽引する。この主導原理のもとに、「生理機能の理解に向けた膜輸送研究」が再び急速に進展すると期待される。また、臨床医学・創薬科学への応用に直結する斬新な視点からの研究成果も期待され、学術的貢献に加え、国民生活や産業界への波及効果も予想される。